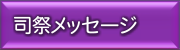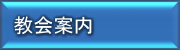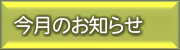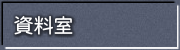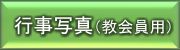信徒のQ&A
ご聖体は1日に2回いただいてもよいですか?
A:(松本神父)
基本的には、一回ですが、例えば、午前に小教会のミサでご聖体を拝領し、午後、玉造のカテドラルでの教区のミサに参加された時など、ご聖体を拝領することが出来ます。
たんに繋がっているのではなく、互いに助け合い感謝し、生かし合う心です。
でも、イエスは、「明日のことまで思い悩むな、その日の苦労は、その日だけで十分である。
そしてイエスが荒れ野で、悪魔から誘惑を受けられた時のことを思い出してください。
「人はパンだけで生きるものではない。
神の口から出る一つ一つの言葉で生きる」と言って悪魔を追い払われたように、一回の聖体拝領は、神の命の言葉と共にある幸いな恵みの糧なのです。
少し聖体をいただくことの幸いを知る信仰をもっと育てましょう。
基本的には、一回ですが、例えば、午前に小教会のミサでご聖体を拝領し、午後、玉造のカテドラルでの教区のミサに参加された時など、ご聖体を拝領することが出来ます。
たんに繋がっているのではなく、互いに助け合い感謝し、生かし合う心です。
でも、イエスは、「明日のことまで思い悩むな、その日の苦労は、その日だけで十分である。
そしてイエスが荒れ野で、悪魔から誘惑を受けられた時のことを思い出してください。
「人はパンだけで生きるものではない。
神の口から出る一つ一つの言葉で生きる」と言って悪魔を追い払われたように、一回の聖体拝領は、神の命の言葉と共にある幸いな恵みの糧なのです。
少し聖体をいただくことの幸いを知る信仰をもっと育てましょう。
お祈りの「使徒信条」に出てくる聖徒の交わりって何のこと?
A:(松本神父)
神さまから創造された被造物は繋がっています。
たんに繋がっているのではなく、互いに助け合い感謝し、生かし合う心です。
聖徒とは、神に繋がり神の心に生き、神の心に仕える愛の命です。
神の国の人たちです。
私たちが慕う聖人たちだけでなく、私たちの知らない神さまだけがご存知のすべての聖徒たちはいつも交わり、助け合っています。
また、この世に生きる私たちのために、いつも恵みを注ぎ、導いて下さっています。
私たちは、それに応え感謝し、ミサ、祈り、犠牲、愛の業によって、助け合って生きる心です。
少し前のカトリック要理は、このように書かれています。
「諸聖徒の交わりとは、キリストの神秘体の属するものがすべて、神の生命と愛によって結ばれており、互いに助け合うことです。 そして、これはこの世に生活する信徒の間だけでなく、天国に楽しむ聖人たちにも煉獄に苦しむ霊魂にも及びます」
罪とは、その助け合う業にシャッターを降ろし、邪魔することです。
私たち信者は、信仰生活を過ごしながら、助け合い、支えあう心を見失っていることが多々あるものです。
皆さん、マリアさんにならって、カトリック信仰の大切な教え、聖徒の交わりに、繋がり、仕える者であれるように祈ってまいりましょう。
神さまから創造された被造物は繋がっています。
たんに繋がっているのではなく、互いに助け合い感謝し、生かし合う心です。
聖徒とは、神に繋がり神の心に生き、神の心に仕える愛の命です。
神の国の人たちです。
私たちが慕う聖人たちだけでなく、私たちの知らない神さまだけがご存知のすべての聖徒たちはいつも交わり、助け合っています。
また、この世に生きる私たちのために、いつも恵みを注ぎ、導いて下さっています。
私たちは、それに応え感謝し、ミサ、祈り、犠牲、愛の業によって、助け合って生きる心です。
少し前のカトリック要理は、このように書かれています。
「諸聖徒の交わりとは、キリストの神秘体の属するものがすべて、神の生命と愛によって結ばれており、互いに助け合うことです。 そして、これはこの世に生活する信徒の間だけでなく、天国に楽しむ聖人たちにも煉獄に苦しむ霊魂にも及びます」
罪とは、その助け合う業にシャッターを降ろし、邪魔することです。
私たち信者は、信仰生活を過ごしながら、助け合い、支えあう心を見失っていることが多々あるものです。
皆さん、マリアさんにならって、カトリック信仰の大切な教え、聖徒の交わりに、繋がり、仕える者であれるように祈ってまいりましょう。
合同慰霊祭では希望すれば信者でない祖先のためにも祈っていただけますか?
A:(松本神父)
もちろん心から、喜んで祈ります。
名前を書いて依頼ください。
葬儀の場合は信者さんでない方を教会で葬儀する時は、ミサでなく、集会祭儀の形式でいたします。
祈りは愛ですから、誰にゆだねるのか、誰が守るのか、両者の関わりの心が大切です。
イエスさま、あなたにゆだねますが、私たちの心です。
そして、震災で亡くなられた方のためにと言ったように、合同慰霊祭に、祈りをささげるのは、大切なことです。
もちろん心から、喜んで祈ります。
名前を書いて依頼ください。
葬儀の場合は信者さんでない方を教会で葬儀する時は、ミサでなく、集会祭儀の形式でいたします。
祈りは愛ですから、誰にゆだねるのか、誰が守るのか、両者の関わりの心が大切です。
イエスさま、あなたにゆだねますが、私たちの心です。
そして、震災で亡くなられた方のためにと言ったように、合同慰霊祭に、祈りをささげるのは、大切なことです。
洗礼名をつけるときの決まり(ルール)はありますか。
洗礼名は聖人の名前をいただくと決まっているのではないのでしょうか。
洗礼名は聖人の名前をいただくと決まっているのではないのでしょうか。
A:(松本神父)
洗礼名は霊名とも言われ、神の子としての新たな生命の誕生を祝う秘跡の恵みの名です。
天の諸聖人たちの名をいただいて、その聖徳を模範として生きるために、またご保護やとりなしを願って、聖人の名をいただくのが一般的です。
でも、聖人でない名を付けることもあります。
先月の榎並息吹君は、プネウマ(聖霊、息)でしたし、ノエル(クリスマス)と言った名の方もおられます。
教会法典は、キリスト教的センスになじまない名は避けるようにとあります
大切なのは、いただいた洗礼名を愛し、毎日、自分の洗礼名を呼び、洗礼名の聖人を家族の一員として親しみ、喜んで信仰を生きることです。
洗礼名は霊名とも言われ、神の子としての新たな生命の誕生を祝う秘跡の恵みの名です。
天の諸聖人たちの名をいただいて、その聖徳を模範として生きるために、またご保護やとりなしを願って、聖人の名をいただくのが一般的です。
でも、聖人でない名を付けることもあります。
先月の榎並息吹君は、プネウマ(聖霊、息)でしたし、ノエル(クリスマス)と言った名の方もおられます。
教会法典は、キリスト教的センスになじまない名は避けるようにとあります
大切なのは、いただいた洗礼名を愛し、毎日、自分の洗礼名を呼び、洗礼名の聖人を家族の一員として親しみ、喜んで信仰を生きることです。
イエスは金曜日に亡くなり、3日目に復活されたのなら、月曜日になる?
A:(松本神父)
イエスは、ユダヤ人が大切に守っている安息日の前に、十字架に架けられ亡くなられた。
そして、安息日が始まるので、急いで十字架から下ろされ墓に葬られた。
ユダヤ人の安息日は、土曜日ですから、イエスが亡くなられたのは金曜日。
3日目とは、金、土、そして、日です。
だから、以前の教会の復活徹夜祭は、日曜日の午前O時から始まりました。
今では、ほとんどの教会は、聖土曜日の夜に行われています。
甲子園教会も夜7時からでした。
一番大切な祝い、クリスマスの深夜ミサと復活徹夜祭は、すっかり前日になってしまっている。
人が神さまに仕えるのではなく、神さまを人に仕えさせている。
その方が楽だし、都合がいいから。
だから、徹夜祭と言う言葉は、形式的な言葉になっている。
これでいいのかなと時々思う。
イエスは、ユダヤ人が大切に守っている安息日の前に、十字架に架けられ亡くなられた。
そして、安息日が始まるので、急いで十字架から下ろされ墓に葬られた。
ユダヤ人の安息日は、土曜日ですから、イエスが亡くなられたのは金曜日。
3日目とは、金、土、そして、日です。
だから、以前の教会の復活徹夜祭は、日曜日の午前O時から始まりました。
今では、ほとんどの教会は、聖土曜日の夜に行われています。
甲子園教会も夜7時からでした。
一番大切な祝い、クリスマスの深夜ミサと復活徹夜祭は、すっかり前日になってしまっている。
人が神さまに仕えるのではなく、神さまを人に仕えさせている。
その方が楽だし、都合がいいから。
だから、徹夜祭と言う言葉は、形式的な言葉になっている。
これでいいのかなと時々思う。
仏教では1周忌、3回忌、7回忌のような年忌法要を行いますが、カトリックでもそれに相当するものがありますか?
A:(松本神父)
「忌む」という字は、死者のために、神に祈るにあたり、汚れた心身を清める心です。
亡くなった大切な方の命日にあたり、心して祈る、それが法要です。
カトリック教会も同じ。
皆さんも、ミサを依頼され、記念の祈りをされているではありませんか。
日本では、仏教の方が多いので、教会は、仏教の習慣に出来るだけ応えられるよう配慮しているのです。
よく49日と言いますが、教会では、50日祭と言っています。
聖霊降臨の心です。
イエスが十字架上で亡くなった後、弟子たちは聖母マリアと共に、熱心に祈っていましたが、 突然、聖霊が下り、目が開け、イエスを裏切った弟子たちが、イエスのために命を捧げる証し人に変ったように、 愛する人を失った悲しみから、慰めと希望に代わる恵みの祈りなのです。
ある方は命日などに、必ずミサを依頼されていますが、皆さんも、年に一度ぐらいは、先祖と家庭のために、ミサを依頼され祈ることは、大切なことではないでしょうか。
それに皆さんは、結婚記念日や誕生日を祝っているではありませんか。
亡くなった人とともに、今、生きている幸いをもっと大切にしましょう。
それが記念日なのです。
だから、教会は、クリスマスや復活祭を祝い、聖人たちの記念日を大切にし祝っているのです。
「忌む」という字は、死者のために、神に祈るにあたり、汚れた心身を清める心です。
亡くなった大切な方の命日にあたり、心して祈る、それが法要です。
カトリック教会も同じ。
皆さんも、ミサを依頼され、記念の祈りをされているではありませんか。
日本では、仏教の方が多いので、教会は、仏教の習慣に出来るだけ応えられるよう配慮しているのです。
よく49日と言いますが、教会では、50日祭と言っています。
聖霊降臨の心です。
イエスが十字架上で亡くなった後、弟子たちは聖母マリアと共に、熱心に祈っていましたが、 突然、聖霊が下り、目が開け、イエスを裏切った弟子たちが、イエスのために命を捧げる証し人に変ったように、 愛する人を失った悲しみから、慰めと希望に代わる恵みの祈りなのです。
ある方は命日などに、必ずミサを依頼されていますが、皆さんも、年に一度ぐらいは、先祖と家庭のために、ミサを依頼され祈ることは、大切なことではないでしょうか。
それに皆さんは、結婚記念日や誕生日を祝っているではありませんか。
亡くなった人とともに、今、生きている幸いをもっと大切にしましょう。
それが記念日なのです。
だから、教会は、クリスマスや復活祭を祝い、聖人たちの記念日を大切にし祝っているのです。
ベールには白いベールと黒いベールがありますが、どのように違うのでしょうか。
また、お葬式に白いベールを被ってもよいでしょうか。
また、お葬式に白いベールを被ってもよいでしょうか。
A:(松本神父)
白でも黒でもかまいません。
大切なのは、ベールをつけ、神への畏敬、謙遜な心をささげることが大切です。
色はその時の心を表現するものです。
教会の典礼の色は、白は復活、命、喜び。
それで、クリスマスや復活祭を白で祝い、葬儀の悲しみ、苦しみの時は黒。
四旬節の試練の時は紫。
殉教者の時は愛の赤。
年間の時は希望の緑の祭服を使います。
だから、葬儀に参列される方は黒い喪服を着られるのでしょう。
黒いベールは、一般的な慣習で、既婚者の方がされているようです。
教会の典礼暦は、白、紫、黒の表示があり、司祭が自由に選択することになっています。
以前は葬儀の時、黒の祭服でしたが、通常は、紫の祭服でささげられています。
でも最近は、悲しみよりも希望を示す、復活の白の祭服で、ミサをささげることも多くなってきました。
葬儀の時は、遺族の方への配慮から、黒っぽい服装で参列され、ベールは、白でも、黒でもかまいません。
黒いベールを持っておられたら、黒いベールをされるのもいいでしょう。
白でも黒でもかまいません。
大切なのは、ベールをつけ、神への畏敬、謙遜な心をささげることが大切です。
色はその時の心を表現するものです。
教会の典礼の色は、白は復活、命、喜び。
それで、クリスマスや復活祭を白で祝い、葬儀の悲しみ、苦しみの時は黒。
四旬節の試練の時は紫。
殉教者の時は愛の赤。
年間の時は希望の緑の祭服を使います。
だから、葬儀に参列される方は黒い喪服を着られるのでしょう。
黒いベールは、一般的な慣習で、既婚者の方がされているようです。
教会の典礼暦は、白、紫、黒の表示があり、司祭が自由に選択することになっています。
以前は葬儀の時、黒の祭服でしたが、通常は、紫の祭服でささげられています。
でも最近は、悲しみよりも希望を示す、復活の白の祭服で、ミサをささげることも多くなってきました。
葬儀の時は、遺族の方への配慮から、黒っぽい服装で参列され、ベールは、白でも、黒でもかまいません。
黒いベールを持っておられたら、黒いベールをされるのもいいでしょう。
カトリックとプロテスタントとどう違うの?(KYIさん・学生)
A:(松本神父)
何よりも大切なことは、違いを強調するより、同じことを理解し合う心を育てることです。
だって、同じ三位一体の神を信仰する仲間なのですから。
と言っても相違点はいろいろ見られます。
学生の方だから、カトリック教会の教えをしっかりと学んでくださいますように。
きょうは、一つのことにふれたいと思います。
それは、祭壇と位階制度の有無です。
カトリックの聖堂の中心は祭壇ですが、プロテスタントには祭壇がなく、代わりに説教台が中心です。
祭壇はいけにえの場、神が人の赦し、清め、命のために、いけにえとなってくださる有難い場。
それは、人間にはできません。
唯一、イエスが託された教皇が、その教皇が任命された司教、司教が任命された司祭が、イエスの業を行使できるのです。
そのイエスの唯一永遠の十字架のいけにえの恵みが、今もあることを示すのが祭壇。
それが祭司職。
カトリック教会は、イエスの死と復活の後、キリストの代理者ペトロと歴代の教皇、その位階制度を大切にしながら発展した共同体ですが、16世紀に大きな変化が起こります。
カトリック教会にルターがプロテスト(抗議)して、最終的に、カトリックを離れ、聖書を拠り所とし、位階制度を廃止した教会が生まれました。
それがプロテスタント教会です。
イギリスの教会では、教皇に代わって、国王がその座につく聖公会が生まれました。
それに対して、混乱する教会をイエズス会の創立者、イグナチオ・ロヨラらは、教皇の座を尊敬し、教皇を中心とする教会を建直したのが今日のカトリック教会です。
司祭の召命が少なく、司祭のいない教会が増えてきている今日のカトリック教会の現状は、カトリック教会の信者共同体に、祭司職の尊さ、大切さの信仰が弱くなっていることでもあるのではと思ったりしています。
青年の皆さん、司祭を送ってくださるように祈ってください。
そしてあなたも「主よ、司祭への道にわたしたちを呼んでください」と祈ってください。
司祭がいなくなることは、カトリック教会がなくなることですから。
何よりも大切なことは、違いを強調するより、同じことを理解し合う心を育てることです。
だって、同じ三位一体の神を信仰する仲間なのですから。
と言っても相違点はいろいろ見られます。
学生の方だから、カトリック教会の教えをしっかりと学んでくださいますように。
きょうは、一つのことにふれたいと思います。
それは、祭壇と位階制度の有無です。
カトリックの聖堂の中心は祭壇ですが、プロテスタントには祭壇がなく、代わりに説教台が中心です。
祭壇はいけにえの場、神が人の赦し、清め、命のために、いけにえとなってくださる有難い場。
それは、人間にはできません。
唯一、イエスが託された教皇が、その教皇が任命された司教、司教が任命された司祭が、イエスの業を行使できるのです。
そのイエスの唯一永遠の十字架のいけにえの恵みが、今もあることを示すのが祭壇。
それが祭司職。
カトリック教会は、イエスの死と復活の後、キリストの代理者ペトロと歴代の教皇、その位階制度を大切にしながら発展した共同体ですが、16世紀に大きな変化が起こります。
カトリック教会にルターがプロテスト(抗議)して、最終的に、カトリックを離れ、聖書を拠り所とし、位階制度を廃止した教会が生まれました。
それがプロテスタント教会です。
イギリスの教会では、教皇に代わって、国王がその座につく聖公会が生まれました。
それに対して、混乱する教会をイエズス会の創立者、イグナチオ・ロヨラらは、教皇の座を尊敬し、教皇を中心とする教会を建直したのが今日のカトリック教会です。
司祭の召命が少なく、司祭のいない教会が増えてきている今日のカトリック教会の現状は、カトリック教会の信者共同体に、祭司職の尊さ、大切さの信仰が弱くなっていることでもあるのではと思ったりしています。
青年の皆さん、司祭を送ってくださるように祈ってください。
そしてあなたも「主よ、司祭への道にわたしたちを呼んでください」と祈ってください。
司祭がいなくなることは、カトリック教会がなくなることですから。
死ぬのが怖いのは、信仰が薄いからでしょうか
A:(松本神父)
死ぬのか怖いと言うのは、健康な心、それが普通。問題は、怖さをどう受け止めるかです。
問題は、怖さをどう受け止めるかです。
誰も免れることが出来ない死を、誰も生きている間、自分で経験できない、それが死。
唯一、その死を滅ぼされたのが、神であり、人であるイエス。それでイエス・キリストと言うの。
それでイエス・キリストと言うの。
子が親に委ねきって、安心しているように、人がイエスに委ねられるかが、信仰と言うもの。
人間イエスは、人生の最後の夜ゲッセマネで、「わたしは死ぬばかりに悲しい」と悶えられました。
その後が大事です。
「この苦しみが過ぎ去るように祈られ、わが思いではなく、御心のままに」と、御父に委ねられ、「時が来た」と言われ、死を乗り越えられました。
イエスに委ねる愛、信仰が、復活の恵み、命なのです。
イエスは、弟子に言われました。
「心は燃えていても、肉体は弱い」と。
私たちの姿です。
それで、ミサに預かり祈るのです。
ミサは、イエスの死の記念、復活、永遠の命の糧に預かる恵みなのですから。
アーメン。
死ぬのか怖いと言うのは、健康な心、それが普通。問題は、怖さをどう受け止めるかです。
問題は、怖さをどう受け止めるかです。
誰も免れることが出来ない死を、誰も生きている間、自分で経験できない、それが死。
唯一、その死を滅ぼされたのが、神であり、人であるイエス。それでイエス・キリストと言うの。
それでイエス・キリストと言うの。
子が親に委ねきって、安心しているように、人がイエスに委ねられるかが、信仰と言うもの。
人間イエスは、人生の最後の夜ゲッセマネで、「わたしは死ぬばかりに悲しい」と悶えられました。
その後が大事です。
「この苦しみが過ぎ去るように祈られ、わが思いではなく、御心のままに」と、御父に委ねられ、「時が来た」と言われ、死を乗り越えられました。
イエスに委ねる愛、信仰が、復活の恵み、命なのです。
イエスは、弟子に言われました。
「心は燃えていても、肉体は弱い」と。
私たちの姿です。
それで、ミサに預かり祈るのです。
ミサは、イエスの死の記念、復活、永遠の命の糧に預かる恵みなのですから。
アーメン。
聖書の話は本当ですか
A:(松本神父)
聖書は生命の書。
あなたがいろんな体験をかさねながら、一生涯、聖書と付き合いながら、神さまに、この話ホント?と聴きながら、自分も考え、祈りながら、本当かどうか、あなたの心が決めるもの。
わたしは聖書を信じていますから、毎日聖書を読み、いつも何かハッとさせられ、恵みの糧をいただいています。
聖書は愛の書。
あなたが神さまを好きになればなるほど、聖書の言葉が心に響いてくると思うよ。
だって、聖書は、神さまのあなたへのラブ・レターだもの。
典礼聖歌の52番「神のはからいは限りなく、生涯わたしは、その中に生きる」は、とっても美しく深い歌。
よければ、この歌を、生涯歌い続けてほしいな。
きっと、答えが出ると思うよ。
聖書は生命の書。
あなたがいろんな体験をかさねながら、一生涯、聖書と付き合いながら、神さまに、この話ホント?と聴きながら、自分も考え、祈りながら、本当かどうか、あなたの心が決めるもの。
わたしは聖書を信じていますから、毎日聖書を読み、いつも何かハッとさせられ、恵みの糧をいただいています。
聖書は愛の書。
あなたが神さまを好きになればなるほど、聖書の言葉が心に響いてくると思うよ。
だって、聖書は、神さまのあなたへのラブ・レターだもの。
典礼聖歌の52番「神のはからいは限りなく、生涯わたしは、その中に生きる」は、とっても美しく深い歌。
よければ、この歌を、生涯歌い続けてほしいな。
きっと、答えが出ると思うよ。
ローマン・カラーについて教えてください
A:(松本神父)
カトリック司祭のしるしであるローマン・カラーです。
ローマン・カラーはある時代のファッションからカトリック司祭のシンボルになりました。
黒又は灰色のシャツに、首の喉仏(のどぼとけ)のところが白色。
シンプルで、オシャレ。
黒は死、白は復活。
喉仏は、英語でアダムのりんごと言います。
つまり、最初の人間、アダムとエバは、罪を犯し、死を招きました。
イエスのお手伝いをする司祭は、その罪、死から救う復活、新しい命を招く役割りが司祭の使命。
そのしるしが、ローマン・カラーなのです。
でも、先月のシスターのベールのように、司祭もローマン・カラーをしない司祭も多くなっています。
かえって、プロテスタントの牧師がされていたり。
今日の教会は、ミサの時の信徒のベール、司祭のローマン・カラー、修道女の修道服など、いろんな事が曖昧なのです。
わたしはやはり伝統あるローマン・カラーをきちんとするのがいいと思っています。
ミサの時など、公式の時、司教、司祭が私服より、きちんとローマン・カラーをし、ベールを脱がれたシスターもミサの時は、ベールを着け、信徒もきちんとした服装、ベールをされた方がいいのではと思っています。
カトリック司祭のしるしであるローマン・カラーです。
ローマン・カラーはある時代のファッションからカトリック司祭のシンボルになりました。
黒又は灰色のシャツに、首の喉仏(のどぼとけ)のところが白色。
シンプルで、オシャレ。
黒は死、白は復活。
喉仏は、英語でアダムのりんごと言います。
つまり、最初の人間、アダムとエバは、罪を犯し、死を招きました。
イエスのお手伝いをする司祭は、その罪、死から救う復活、新しい命を招く役割りが司祭の使命。
そのしるしが、ローマン・カラーなのです。
でも、先月のシスターのベールのように、司祭もローマン・カラーをしない司祭も多くなっています。
かえって、プロテスタントの牧師がされていたり。
今日の教会は、ミサの時の信徒のベール、司祭のローマン・カラー、修道女の修道服など、いろんな事が曖昧なのです。
わたしはやはり伝統あるローマン・カラーをきちんとするのがいいと思っています。
ミサの時など、公式の時、司教、司祭が私服より、きちんとローマン・カラーをし、ベールを脱がれたシスターもミサの時は、ベールを着け、信徒もきちんとした服装、ベールをされた方がいいのではと思っています。
神父さまは365日ミサをしているの?
A:(松本神父)
命は、神さまからいただいているの。
神さまはわたしが生きるために、自分の命を捧げてくださっているの。
だって、人間は食べなければ死んでしまうから。
みんなも毎日、食事しているでしょう。
それで司祭は、感謝して、すべての人の代表として、毎日、神さまに、「ありがとう」の感謝のミサを捧げているの。
憶えていますか。
ミサの時「感謝の祭儀を祝う前に、こころをあらためましょう」と言って、回心のお祈りをしているでしょう。
わたしは、司祭になって、36年になりますが、毎日ミサを捧げることの大切さが解かってきました。
それで、甲子園教会でも、毎朝、シスターや信者さんとミサを捧げているのです。
子どもたちも休みになったら、ラジオ体操のように、教会に来て、一緒にミサを捧げましょう。
イエスさま、きっと喜ばれますよ。 アーメン。
命は、神さまからいただいているの。
神さまはわたしが生きるために、自分の命を捧げてくださっているの。
だって、人間は食べなければ死んでしまうから。
みんなも毎日、食事しているでしょう。
それで司祭は、感謝して、すべての人の代表として、毎日、神さまに、「ありがとう」の感謝のミサを捧げているの。
憶えていますか。
ミサの時「感謝の祭儀を祝う前に、こころをあらためましょう」と言って、回心のお祈りをしているでしょう。
わたしは、司祭になって、36年になりますが、毎日ミサを捧げることの大切さが解かってきました。
それで、甲子園教会でも、毎朝、シスターや信者さんとミサを捧げているのです。
子どもたちも休みになったら、ラジオ体操のように、教会に来て、一緒にミサを捧げましょう。
イエスさま、きっと喜ばれますよ。 アーメン。
なぜ、シスターの修道会はヴェールをかぶらないのですか?
A:(Sr.陰山和子 ・援助マリア修道会 西宮修道院)
私は一人の「援助マリア修道会会員」としてこの質問にお答えします。なぜなら修道者は各修道会が「教会の公認の下」にその「会憲」に従い、それぞれに 修道服を着用しているからです。援助マリア修道会はトラピストやカルメル会のような観想修道会ではなく教皇直轄の使徒的修道会です。私たちは教皇庁認可 のもと、その「会憲」に従い与えられた修道服を受け「福音的勧告」の生活を生きています。修道服は「その時代と社会的状況に適い、簡素で慎み深く、質 素、端正、さらに健康、地域や季節に適応したものであること」が勧められています。<修道生活刷新の教例17>
私の「現実の宣教活動からの体験」を分かち合いましょう。ヴェールを付けて病院訪問をした時「そんな格好で来てくれるな」と拒否されることや「あんな 格好している人に世の中の相談をしたって通じやしないよ」とか「お祈り三昧ですか」と駅でからまれたり「団体で睨まれる」ことなどは主キリストと共に耐 えることは容易です。しかし「先生、先生」と下にも置かない扱いや「私たちと違う人間」、「清らかな人なんやで」(ヴェールは「貞潔」のシンボル)「学 識の高い人たちしかなれんのよ」と言われたりすることは、真実の理解とは程遠く援助マリア修道会の「かかわりの宣教」の大きな妨げになります。そこで私 は慎重に「識別」し指導を受けました。そしてしっかりと「心にキリストを着ること」こそを選び決意したのです。今は一人の仲間として「弱さの中にある きょうだいたちと同じサークルの一人」になれますし、沢山の「行き場のないきょうだいたち」が親しげに腹を割った話をしてくださること、「地域の家庭の いざこざ相談」「ああ、生きていてよかった」「ここに来てよかった」「また来ていいですか」「家に来てください」と言って頂けることが沢山増え、自由に そして容易に宣教に励むことができて喜んでいます。
松本神父様がはじめに皆さまに「どうぞヴェールが信仰の助けになるならば自由にお付けください」と言われた言葉はとても大切な一言です。信仰はキリス トにおける自由と喜びの中で成長しますから。
援助マリア修道会の奉献の印は十字架と「わたしはあなたを選んだ。主よここにいます。わたしを遣わしください」<イザヤ6:8・会憲35>と刻まれて いる指輪です。自分の生涯を奉献する終世誓願の時、私は次のような 「ことば」を頂きました。
「キリストのために人を失い、キリストのために物を失い、キリストのために自分自身を失う。」
奉献生活者にとって一番大切なことは何か。それはキリストにこそ生きる こと。私はキリスト様に心魅かれて福音的勧告を生きつつ神のきょうだい たちへの奉仕を望み「修道者」になりました。「低みから歩みを起こされ る」よい神である主と共に、置かれた場に応じて「今」の私を生きてゆく ことが「招かれている道」だと確信しています。
私は一人の「援助マリア修道会会員」としてこの質問にお答えします。なぜなら修道者は各修道会が「教会の公認の下」にその「会憲」に従い、それぞれに 修道服を着用しているからです。援助マリア修道会はトラピストやカルメル会のような観想修道会ではなく教皇直轄の使徒的修道会です。私たちは教皇庁認可 のもと、その「会憲」に従い与えられた修道服を受け「福音的勧告」の生活を生きています。修道服は「その時代と社会的状況に適い、簡素で慎み深く、質 素、端正、さらに健康、地域や季節に適応したものであること」が勧められています。<修道生活刷新の教例17>
私の「現実の宣教活動からの体験」を分かち合いましょう。ヴェールを付けて病院訪問をした時「そんな格好で来てくれるな」と拒否されることや「あんな 格好している人に世の中の相談をしたって通じやしないよ」とか「お祈り三昧ですか」と駅でからまれたり「団体で睨まれる」ことなどは主キリストと共に耐 えることは容易です。しかし「先生、先生」と下にも置かない扱いや「私たちと違う人間」、「清らかな人なんやで」(ヴェールは「貞潔」のシンボル)「学 識の高い人たちしかなれんのよ」と言われたりすることは、真実の理解とは程遠く援助マリア修道会の「かかわりの宣教」の大きな妨げになります。そこで私 は慎重に「識別」し指導を受けました。そしてしっかりと「心にキリストを着ること」こそを選び決意したのです。今は一人の仲間として「弱さの中にある きょうだいたちと同じサークルの一人」になれますし、沢山の「行き場のないきょうだいたち」が親しげに腹を割った話をしてくださること、「地域の家庭の いざこざ相談」「ああ、生きていてよかった」「ここに来てよかった」「また来ていいですか」「家に来てください」と言って頂けることが沢山増え、自由に そして容易に宣教に励むことができて喜んでいます。
松本神父様がはじめに皆さまに「どうぞヴェールが信仰の助けになるならば自由にお付けください」と言われた言葉はとても大切な一言です。信仰はキリス トにおける自由と喜びの中で成長しますから。
援助マリア修道会の奉献の印は十字架と「わたしはあなたを選んだ。主よここにいます。わたしを遣わしください」<イザヤ6:8・会憲35>と刻まれて いる指輪です。自分の生涯を奉献する終世誓願の時、私は次のような 「ことば」を頂きました。
「キリストのために人を失い、キリストのために物を失い、キリストのために自分自身を失う。」
奉献生活者にとって一番大切なことは何か。それはキリストにこそ生きる こと。私はキリスト様に心魅かれて福音的勧告を生きつつ神のきょうだい たちへの奉仕を望み「修道者」になりました。「低みから歩みを起こされ る」よい神である主と共に、置かれた場に応じて「今」の私を生きてゆく ことが「招かれている道」だと確信しています。
かつて教会にはカトリック信者として守るべき「5つの掟」があったと思いますが、今、ほとんど聞かれません。
今もこの「掟」は生きているのでしょうか。
今もこの「掟」は生きているのでしょうか。
A:(松本神父)
勿論、今も大切な教え、カトリック教会共同体の要(かなめ)です。
この教えが曖昧なので、気づかないうちに、畏敬の心、感謝の心が弱くなり、 主日にミサに預かる恵み、ゆるしの秘跡、聖体をいただく有難さの心が失われ、 神さまに仕える喜びよりも、神さまを自分に仕えさせているといったことになっているのではないでしょうか。
教会維持費も、半数近くの方がされていないのが現状なのです。
復活祭を迎えた私たちです。
カトリックの原点を生きる生活に根づいた、神さまあなたのおかげですと言った、感謝の信仰を取り戻し、新たに頑張りたいものです。
勿論、今も大切な教え、カトリック教会共同体の要(かなめ)です。
この教えが曖昧なので、気づかないうちに、畏敬の心、感謝の心が弱くなり、 主日にミサに預かる恵み、ゆるしの秘跡、聖体をいただく有難さの心が失われ、 神さまに仕える喜びよりも、神さまを自分に仕えさせているといったことになっているのではないでしょうか。
教会維持費も、半数近くの方がされていないのが現状なのです。
復活祭を迎えた私たちです。
カトリックの原点を生きる生活に根づいた、神さまあなたのおかげですと言った、感謝の信仰を取り戻し、新たに頑張りたいものです。
ミサでの言葉の典礼の時、神父さまは福音朗読の前に「○○による福音」と唱え、信徒は「主に栄光」と答えます。
その時に額と口と胸に十字を切る人と一礼だけする人がいますが、どちらが正しいのでしょうか?
その時に額と口と胸に十字を切る人と一礼だけする人がいますが、どちらが正しいのでしょうか?
A:(松本神父)
荒野における誘いの時、イエスは、「人はパンだけで生きるのではない。
神の口から出る一つひとつの言葉によって生きる」と言って悪魔を退けました。
でもイエスと違って、いつも悪魔の誘いに負けている私たちです。
ミサにおける福音朗読は、そのイエスの言葉を聞く時ですから、 「額」、考えにおいて、「口」、言葉において、「胸」、心において、悪魔に負ける私の思いではなく、 「退けサタン」と、悪魔に打ち勝つイエスに、仕えて生きたいと願う私たちの心の姿勢を示す「しるし」なのです。
ミサの福音朗読は、単なる聖書の言葉を聞くのではなく、まさに今、イエスの言葉を聞くのですから。
バチカン公会議で、形式的な形よりも、内面を大切にと言ったことが強調されるようになり、安易に、教会の伝統を、古いものとしてきた事も事実です。
大切なのは、神に出会う幸いのために、自分は、どのような振る舞いが、ふさわしいか、素直に振り返ってみる時が来ているように思います。
第二バチカン公会議の開催は1962~65年でした。
まさに揺りかごから墓場まで、すべてにおいて神さまからの祝福を受けることは、健全な信仰生活ではないでしょうか。
そして、私が洗礼の恵みを受けたのは64年でした。
荒野における誘いの時、イエスは、「人はパンだけで生きるのではない。
神の口から出る一つひとつの言葉によって生きる」と言って悪魔を退けました。
でもイエスと違って、いつも悪魔の誘いに負けている私たちです。
ミサにおける福音朗読は、そのイエスの言葉を聞く時ですから、 「額」、考えにおいて、「口」、言葉において、「胸」、心において、悪魔に負ける私の思いではなく、 「退けサタン」と、悪魔に打ち勝つイエスに、仕えて生きたいと願う私たちの心の姿勢を示す「しるし」なのです。
ミサの福音朗読は、単なる聖書の言葉を聞くのではなく、まさに今、イエスの言葉を聞くのですから。
バチカン公会議で、形式的な形よりも、内面を大切にと言ったことが強調されるようになり、安易に、教会の伝統を、古いものとしてきた事も事実です。
大切なのは、神に出会う幸いのために、自分は、どのような振る舞いが、ふさわしいか、素直に振り返ってみる時が来ているように思います。
第二バチカン公会議の開催は1962~65年でした。
まさに揺りかごから墓場まで、すべてにおいて神さまからの祝福を受けることは、健全な信仰生活ではないでしょうか。
そして、私が洗礼の恵みを受けたのは64年でした。
家や車なども祝別していただけるそうですが、毎日の生活の中で祝福や祝別をどんなとき、どんなものにいただけるのでしょうか。
A:(松本神父)
すべてのものは、神さまからいただいたものです。
だから、その神さまの恵みに感謝の心で立ち返り、新たにスタートする恵みをいただくことは大切なことです。
特に、生活の節目において。
赤ちゃんを授かり、赤ちゃんを守る腹帯の祝別。
七五三、成人式などは日本の社会生活の中に深く寝付いた習慣でしょうか。
地鎮祭、家や車の祝別もそうです。
そして当然十字架やロザリオといった信心用具の祝別など。
まさに揺りかごから墓場まで、すべてにおいて神さまからの祝福を受けることは、健全な信仰生活ではないでしょうか。
私は何となく信者の方で、腹帯は中山寺へ、厄払いは神社にと言ったことをされておられるのではと思います。
皆さん、すべてのことを、親である神さまに委ねて、守られ、喜び、感謝する生活が息づく信仰を育てましょう。
気軽に司祭に依頼してくださいますように。
親の神さまも喜ばれることでしょう。
すべてのものは、神さまからいただいたものです。
だから、その神さまの恵みに感謝の心で立ち返り、新たにスタートする恵みをいただくことは大切なことです。
特に、生活の節目において。
赤ちゃんを授かり、赤ちゃんを守る腹帯の祝別。
七五三、成人式などは日本の社会生活の中に深く寝付いた習慣でしょうか。
地鎮祭、家や車の祝別もそうです。
そして当然十字架やロザリオといった信心用具の祝別など。
まさに揺りかごから墓場まで、すべてにおいて神さまからの祝福を受けることは、健全な信仰生活ではないでしょうか。
私は何となく信者の方で、腹帯は中山寺へ、厄払いは神社にと言ったことをされておられるのではと思います。
皆さん、すべてのことを、親である神さまに委ねて、守られ、喜び、感謝する生活が息づく信仰を育てましょう。
気軽に司祭に依頼してくださいますように。
親の神さまも喜ばれることでしょう。
「ゆるしの秘跡」を受けるにあたり、こんなことを告白したら神父様にどのように思われるだろうか、と心配したり、毎回同じことを告白してしまうのですが・・・
A:(松本神父)
人間は社会の一員として暮らしています。
そして信者は、神と教会の新しい関わりに於いて、学び、導かれ、生活していますが、人間ですから過ちを犯してしまいます。
罪とは、神に背を向けて、孤独な自分の世界をつくり逃げている状態です。
放蕩息子が父親から、離れている状態のようなものです。
そんな時、愛とゆるしの親である神に出会い、また元気を取り戻すのが、赦しの秘跡です。
放蕩息子が父親のもとに帰り、父親に抱きしめられ喜ぶ姿です。
どうして司祭に、自分の弱さ、恥ずかしい罪を告白するのかというと、カトリック教会の司祭職は勉強の結果ではなく、叙階の秘跡によって、司教から、キリストのあがないのみ業、罪をゆるす権能を委ねられているからです
大切なのは、実際に罪を赦しているのは、イエスさまであるということです。
だから、ゆるしの秘跡は、とてつもない大きな恵みではないでしょうか。
何をどう言ったらよいかと心配しないで、神さまを信じて、素直にゆるしを願いたいことを、司祭に告白することです。
きっと、謙遜な澄んだ信仰の喜びをいただかれると思います。
人間は社会の一員として暮らしています。
そして信者は、神と教会の新しい関わりに於いて、学び、導かれ、生活していますが、人間ですから過ちを犯してしまいます。
罪とは、神に背を向けて、孤独な自分の世界をつくり逃げている状態です。
放蕩息子が父親から、離れている状態のようなものです。
そんな時、愛とゆるしの親である神に出会い、また元気を取り戻すのが、赦しの秘跡です。
放蕩息子が父親のもとに帰り、父親に抱きしめられ喜ぶ姿です。
どうして司祭に、自分の弱さ、恥ずかしい罪を告白するのかというと、カトリック教会の司祭職は勉強の結果ではなく、叙階の秘跡によって、司教から、キリストのあがないのみ業、罪をゆるす権能を委ねられているからです
大切なのは、実際に罪を赦しているのは、イエスさまであるということです。
だから、ゆるしの秘跡は、とてつもない大きな恵みではないでしょうか。
何をどう言ったらよいかと心配しないで、神さまを信じて、素直にゆるしを願いたいことを、司祭に告白することです。
きっと、謙遜な澄んだ信仰の喜びをいただかれると思います。
教会の初代教皇は聖ペトロでしたが、2代目は誰ですか。(H.Eくん)
A:(松本神父)
ペトロの後を継いだのは、聖リヌスです。
3代目はアナクレトウス、そして4代目は有名な聖クレメンスです。
迫害や困難の時代に、ペトロたちの使徒の福音を受け継ぎ、私たちの信仰のよりどころとしている聖書。
その聖書のまさに生の生きた聖書である信仰共同体のリーダーであったのです。
聖クレメンスは、教会は政治的な構造ではなく、秘跡的な構造をもつ天からのものと言い、信者に謙遜と兄弟愛の大切さを説いています。
聖クレメンスの「コリントのキリスト者へ」の手紙は、聖書に次ぐ、貴重なものの一つです。。
ペトロの後を継いだのは、聖リヌスです。
3代目はアナクレトウス、そして4代目は有名な聖クレメンスです。
迫害や困難の時代に、ペトロたちの使徒の福音を受け継ぎ、私たちの信仰のよりどころとしている聖書。
その聖書のまさに生の生きた聖書である信仰共同体のリーダーであったのです。
聖クレメンスは、教会は政治的な構造ではなく、秘跡的な構造をもつ天からのものと言い、信者に謙遜と兄弟愛の大切さを説いています。
聖クレメンスの「コリントのキリスト者へ」の手紙は、聖書に次ぐ、貴重なものの一つです。。
信者でない人と結婚した場合、結婚の秘跡を受けることができないと聞きましたが、本当ですか。
結婚の秘跡のお恵みとは具体的にどのようなものですか。(I.Aさん)
結婚の秘跡のお恵みとは具体的にどのようなものですか。(I.Aさん)
A:(松本神父)
結婚は、男女が、愛の誓いを交し合うことにより、夫婦となり家庭を築くことです。
今日ではホテル等結婚式場の多くは、キリスト教形式のようです。
しかし、形は似ていても、神のこと、教えや信仰など抜きにした人間の愛による婚姻と、 信者同志が、ミサの中で、神の助けと導きを願い、聖なる誓いを交し合い、聖体をともに拝領し、 神の祝福をいただき出発するカトリックの婚姻の秘跡とはやはり違います。
神から祝福とその愛に倣う夫婦だから、また離婚を認めないのです。
神に選ばれ、聖なる者、愛されている者として、二人はもはや一体であると神から祝福の恵みをいただくとともに、 二人が夫婦としての使命と責任を担い合い、イエスの人に対する無償の愛に倣って夫婦の愛を育てる愛の家庭は、 神の創造の業に参与する幸い、秘跡の恵みですから、また信仰が伴います。
信者さんでない方と結婚される信者は、相手を神に導く、愛の模範、使命を担っているのです。
信者が結婚する場合、所属の司祭に、その旨を知らせ、手続きが必要です。
最近知らせないまま、何処かで結婚される方がいます。
親に知らせないで、結婚するようなものではないでしょうか。
親が悲しむように、神さまも同じではないでしょうか。
どうぞ、お知らせくださいますように。
神さまが喜んでくださる家庭を築かれますように、アーメン。
結婚は、男女が、愛の誓いを交し合うことにより、夫婦となり家庭を築くことです。
今日ではホテル等結婚式場の多くは、キリスト教形式のようです。
しかし、形は似ていても、神のこと、教えや信仰など抜きにした人間の愛による婚姻と、 信者同志が、ミサの中で、神の助けと導きを願い、聖なる誓いを交し合い、聖体をともに拝領し、 神の祝福をいただき出発するカトリックの婚姻の秘跡とはやはり違います。
神から祝福とその愛に倣う夫婦だから、また離婚を認めないのです。
神に選ばれ、聖なる者、愛されている者として、二人はもはや一体であると神から祝福の恵みをいただくとともに、 二人が夫婦としての使命と責任を担い合い、イエスの人に対する無償の愛に倣って夫婦の愛を育てる愛の家庭は、 神の創造の業に参与する幸い、秘跡の恵みですから、また信仰が伴います。
信者さんでない方と結婚される信者は、相手を神に導く、愛の模範、使命を担っているのです。
信者が結婚する場合、所属の司祭に、その旨を知らせ、手続きが必要です。
最近知らせないまま、何処かで結婚される方がいます。
親に知らせないで、結婚するようなものではないでしょうか。
親が悲しむように、神さまも同じではないでしょうか。
どうぞ、お知らせくださいますように。
神さまが喜んでくださる家庭を築かれますように、アーメン。
堅信とは信仰の道を今後も続けていくとういう意思表明と聞きました。
私は幼児洗礼です。
中学生の頃堅信を受けましたが、成り行きで何も深く考えていませんでした。
もし、「続けていかない」と意思表明したらどうなりますか。
破門でしょうか。
また、堅信式は司教様しかできないのでしょうか。(YMさん)
私は幼児洗礼です。
中学生の頃堅信を受けましたが、成り行きで何も深く考えていませんでした。
もし、「続けていかない」と意思表明したらどうなりますか。
破門でしょうか。
また、堅信式は司教様しかできないのでしょうか。(YMさん)
A:(松本神父)
堅信は、キリストの証人になる信仰の恵み。
以前は、洗礼と堅信が分けられていました。
今日の教会は、洗礼、堅信、聖体は一つのものとしての、本来の姿になるように指導されています。
堅信は、聖霊の恵みを受けること。
それは、教会を通して委ねられた司教の役務です。
ですから、司教の按手、聖香油の塗油によって、聖霊の恵みを受けて、強められ、キリストの証人となる真の力を信者はいただくのです。
その信仰の権威者のしるしとして、キリストの代理者としての杖を司教は持っているのです。
しかし、復活徹夜祭のミサで、司祭は、洗礼、堅信、聖体を授けることが赦されています。
また、司教の認可を司祭が受ける時、司祭も堅信を授けることができます。
子どもたちは、小さい時に洗礼を受けているので、大人になる頃に、証し人としての責任、信仰の自覚、親に頼る受身から、一人の信者としての役割りに目覚める恵みをいただくのです。
夙川ブロックでは、最近、合同の堅信式で、堅信の恵みをいただくようにしています。
そうは言っても、形式的で安易な堅信に望む状態も事実です。
だから、堅信を受ける前に、教えを学び、準備しているのです。
昨年、芦屋での合同堅信式で、堅信の秘跡を受けた甲子園のある方で、それ以来、一度も教会に来られていない方もおられます。
さびしいですね。
でも、堅信は、消えることのない神の恵みの火ですから、また来られ、信者の証しをされるでしょう。
堅信は、キリストの証人になる信仰の恵み。
以前は、洗礼と堅信が分けられていました。
今日の教会は、洗礼、堅信、聖体は一つのものとしての、本来の姿になるように指導されています。
堅信は、聖霊の恵みを受けること。
それは、教会を通して委ねられた司教の役務です。
ですから、司教の按手、聖香油の塗油によって、聖霊の恵みを受けて、強められ、キリストの証人となる真の力を信者はいただくのです。
その信仰の権威者のしるしとして、キリストの代理者としての杖を司教は持っているのです。
しかし、復活徹夜祭のミサで、司祭は、洗礼、堅信、聖体を授けることが赦されています。
また、司教の認可を司祭が受ける時、司祭も堅信を授けることができます。
子どもたちは、小さい時に洗礼を受けているので、大人になる頃に、証し人としての責任、信仰の自覚、親に頼る受身から、一人の信者としての役割りに目覚める恵みをいただくのです。
夙川ブロックでは、最近、合同の堅信式で、堅信の恵みをいただくようにしています。
そうは言っても、形式的で安易な堅信に望む状態も事実です。
だから、堅信を受ける前に、教えを学び、準備しているのです。
昨年、芦屋での合同堅信式で、堅信の秘跡を受けた甲子園のある方で、それ以来、一度も教会に来られていない方もおられます。
さびしいですね。
でも、堅信は、消えることのない神の恵みの火ですから、また来られ、信者の証しをされるでしょう。
イエス様の子孫は存在するんですか?(A.I)
A:(Sr.鈴木)
イエス様の弟子(特に12使徒)から今の私たちまで、イエス様を信じるすべての人は、全部イエス様の子孫です。
イエス様の弟子(特に12使徒)から今の私たちまで、イエス様を信じるすべての人は、全部イエス様の子孫です。
なんでミサのときに歌を歌うのですか?(M.E)
A:(Sr.鈴木)
歌は神様を賛美することです。ミサの中でみんなが一緒にイエス様に近づき、イエス様を賛美し、イエス様をたたえるために歌います。
歌は神様を賛美することです。ミサの中でみんなが一緒にイエス様に近づき、イエス様を賛美し、イエス様をたたえるために歌います。
マリア様とヨゼフ様は、イエス様が死んでからどうしたんですか? (H.E)
A:(Sr.鈴木)
ヨゼフ様は、イエス様が12歳の時のことまでしか聖書の中に書いてありません。
しかし若い時に亡くなったのではないかと言われています。
マリア様は、イエス様が亡くなったあと弟子のお世話をし、一緒に祈りながら生活していました。
亡くなった日はわかりませんが、亡くなったあとまっすぐ神様の元に行かれ、そのお祝い日もあります。
ヨゼフ様は、イエス様が12歳の時のことまでしか聖書の中に書いてありません。
しかし若い時に亡くなったのではないかと言われています。
マリア様は、イエス様が亡くなったあと弟子のお世話をし、一緒に祈りながら生活していました。
亡くなった日はわかりませんが、亡くなったあとまっすぐ神様の元に行かれ、そのお祝い日もあります。
神様の名前はなんでヤーウェなんですか?(A.I)
A:(Sr.鈴木)
神様はあまりにすばらしくて名前はつけられません。
「ヤーウェ」は神様の名前ではありません。
昔イスラエルの人たちは「神様」を「ヤーウェ」と呼んでいました。
今私たちは「主」と呼んでいます。
どんな言い方をしても、神様を言葉で言いつくすことはできません。
>
神様はあまりにすばらしくて名前はつけられません。
「ヤーウェ」は神様の名前ではありません。
昔イスラエルの人たちは「神様」を「ヤーウェ」と呼んでいました。
今私たちは「主」と呼んでいます。
どんな言い方をしても、神様を言葉で言いつくすことはできません。
どうしてホスチアはミサの前はホスチアで、ミサの中で鈴が鳴った時にご聖体になるの?(M.E)
A:(松本神父)
ホスチアというラテン語の意味知ってる?「犠牲(ぎせい)」という意味なの。
イエスさまが生まれた時、ハトが犠牲になったのだよ。
知ってた?
ミサの中で、司祭が、イエスさまの残された言葉を祈った時、鈴が鳴るのは、イエスさまが犠牲になって、ホスチアが聖なるキリストの体になったことを知らせるの。
だから人は、守られ幸せに生きられるの。
ごはんを食べて生きるように、ご聖体をいただいて、信者は生かされているの。
だからミサのことを感謝の祭儀というのだね。
一番大切にしょうね。
ホスチアというラテン語の意味知ってる?「犠牲(ぎせい)」という意味なの。
イエスさまが生まれた時、ハトが犠牲になったのだよ。
知ってた?
ミサの中で、司祭が、イエスさまの残された言葉を祈った時、鈴が鳴るのは、イエスさまが犠牲になって、ホスチアが聖なるキリストの体になったことを知らせるの。
だから人は、守られ幸せに生きられるの。
ごはんを食べて生きるように、ご聖体をいただいて、信者は生かされているの。
だからミサのことを感謝の祭儀というのだね。
一番大切にしょうね。
イエス様の血はどうしてぶどう酒なの?
また、体はどうしてパンなの? (H.E)
また、体はどうしてパンなの? (H.E)
A:(松本神父)
体には、頭、手、足といった目で見える部分や 心臓や血といったかくれて見えない部分がたくさんあるよね。
それらすべての部分がつながり、ひとつになって生きているのが人の体。
体、血という表現は、生きている「命」のこと。
イエスさまは、人の命は、自分で生きているのではなく、生かされている命であることを忘れないで、感謝して生きることを伝えたかったのだね。
だって人は、ごはんや肉、野菜を食べているから、生きていられるのだからね。
それでイエスさまは、十字架上で亡くなられる前の最後の食事の時、毎日いただくパンとぶどう酒を自分の命として、記念として行うように残されたの。
それがミサだよ。
毎日いただくから、いつもイエスさまに生かされ、イエスさまと一緒に生きることになるのだね。
体には、頭、手、足といった目で見える部分や 心臓や血といったかくれて見えない部分がたくさんあるよね。
それらすべての部分がつながり、ひとつになって生きているのが人の体。
体、血という表現は、生きている「命」のこと。
イエスさまは、人の命は、自分で生きているのではなく、生かされている命であることを忘れないで、感謝して生きることを伝えたかったのだね。
だって人は、ごはんや肉、野菜を食べているから、生きていられるのだからね。
それでイエスさまは、十字架上で亡くなられる前の最後の食事の時、毎日いただくパンとぶどう酒を自分の命として、記念として行うように残されたの。
それがミサだよ。
毎日いただくから、いつもイエスさまに生かされ、イエスさまと一緒に生きることになるのだね。
家に仏壇があるのですが、どのような気持ちで手を合わせたら良いのでしょうか?
また法事のとき、お経の一部を「一緒に唱えましょう」と言われる事があります。
仏教に信心がないのに唱えるのは失礼かと思い黙っているのですが、どうしたらよいのか戸惑います。(B.Yさん)
また法事のとき、お経の一部を「一緒に唱えましょう」と言われる事があります。
仏教に信心がないのに唱えるのは失礼かと思い黙っているのですが、どうしたらよいのか戸惑います。(B.Yさん)
A:(松本神父)
どんな気持ちで手を合わすって?
あなたが信じている神さまに手を合わせて祈るのです。
仏壇に手を合わせる姿なのですが、心はあなたが信じている神さまに手を合わせているのです。
そうでなければ、心は分裂しています。
私は司祭ですが、兄弟は仏教です。
法事に参列した時など、お経を聴きながら、心で神さまに、そのひと時をささげています。
法事の時など、通常は、それでいいのです。
でも、それぞれの信仰を求められる時は、わたしはカトリックですと信仰宣言して、心で祈るか、仏教を強制されるのなら、お断りします。
「一緒に唱えましょう」言われたら、聴きながら心を合わせます。
その方がよく祈れるのですと言われたら如何ですか。
祈りは愛のささげものですから、自分の一番信じている心をささげられたらいいと思います。
どんな気持ちで手を合わすって?
あなたが信じている神さまに手を合わせて祈るのです。
仏壇に手を合わせる姿なのですが、心はあなたが信じている神さまに手を合わせているのです。
そうでなければ、心は分裂しています。
私は司祭ですが、兄弟は仏教です。
法事に参列した時など、お経を聴きながら、心で神さまに、そのひと時をささげています。
法事の時など、通常は、それでいいのです。
でも、それぞれの信仰を求められる時は、わたしはカトリックですと信仰宣言して、心で祈るか、仏教を強制されるのなら、お断りします。
「一緒に唱えましょう」言われたら、聴きながら心を合わせます。
その方がよく祈れるのですと言われたら如何ですか。
祈りは愛のささげものですから、自分の一番信じている心をささげられたらいいと思います。
初めて教会に来た友達が正面のキリスト像を見て
「残酷やね、なんか怖い。なんであんな怖いの飾ってるの?」と聞かれて困ってしまいました。
どう答えたらよいのですか? (高校生MKさん)
どう答えたらよいのですか? (高校生MKさん)
A:(松本神父)
ほんとにそうですね。
はじめて血が滴る苦悩の十字架のイエスの姿に接すると、ギョッとさせられますから。
でもその姿が有難いのですよね。
眺める私たちの罪、死から、私たちを清め、命の喜びへと呼び戻すために、私たちのかわりに、苦しみ、死んでくださった、 イエスの贖いの業、愛の姿なのですから。
「わたしは善い羊飼い、わたしは羊のために命を捨てる。」と。
イエスの願いは、「羊もわたしの声を聞き分けて、一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。」ことです。
だから、私たちはいつも、一人の善い羊飼い、イエスの十字架の前に集い、一つの心で、感謝の祈りをささげているのです。
傷ついた人の 姿を、自分と関係のない、他人の目で眺めるのではなく、お父さんのあの痛ましい傷は、私を救ってくれたときの証し。
そんな姿のお父さん、大好き!これが私たちの心。
>
ほんとにそうですね。
はじめて血が滴る苦悩の十字架のイエスの姿に接すると、ギョッとさせられますから。
でもその姿が有難いのですよね。
眺める私たちの罪、死から、私たちを清め、命の喜びへと呼び戻すために、私たちのかわりに、苦しみ、死んでくださった、 イエスの贖いの業、愛の姿なのですから。
「わたしは善い羊飼い、わたしは羊のために命を捨てる。」と。
イエスの願いは、「羊もわたしの声を聞き分けて、一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。」ことです。
だから、私たちはいつも、一人の善い羊飼い、イエスの十字架の前に集い、一つの心で、感謝の祈りをささげているのです。
傷ついた人の 姿を、自分と関係のない、他人の目で眺めるのではなく、お父さんのあの痛ましい傷は、私を救ってくれたときの証し。
そんな姿のお父さん、大好き!これが私たちの心。
尊者、福者、聖者は、天国においても序列があるのでしょうか。(JMさん)
A:(松本神父)
神の国、天国とは、最も小さな者の最も偉大な仕え合う幸いな交わりの世界。
神さまからいただいたすべての命が、神のうちにともに生きる世界。
みんな同じ、神とともにいる家族。
福者と聖人と言った表現は、この世に生きる私たちへの模範として、その時代に生きる者への教会を通して、神から贈られた恵みの命です。
それ故、これらの聖なる者は、神の恩恵を特に豊かに受け、キリスト者として、優れた生き方と死に方をし、教会によって、崇敬に値する者と判断された人々のことです。
でも、マタイ福音の11章11節で、イエスははっきりと言っておられる。
「およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現われなかった。 しかし、天の国で最も小さな者でも、彼よりは偉大である。」と。
洗礼名をいただく私たちの信仰の深まりへの招きでもあるのです。
神の国、天国とは、最も小さな者の最も偉大な仕え合う幸いな交わりの世界。
神さまからいただいたすべての命が、神のうちにともに生きる世界。
みんな同じ、神とともにいる家族。
福者と聖人と言った表現は、この世に生きる私たちへの模範として、その時代に生きる者への教会を通して、神から贈られた恵みの命です。
それ故、これらの聖なる者は、神の恩恵を特に豊かに受け、キリスト者として、優れた生き方と死に方をし、教会によって、崇敬に値する者と判断された人々のことです。
でも、マタイ福音の11章11節で、イエスははっきりと言っておられる。
「およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現われなかった。 しかし、天の国で最も小さな者でも、彼よりは偉大である。」と。
洗礼名をいただく私たちの信仰の深まりへの招きでもあるのです。
これまで、聖堂に入る時と出る時は入口横の聖水で十字をきるよう
に教わったと記憶していましたが、最近、ミサの後聖堂を出るときは聖
水で十字をきる行為はしないということを聞きましたが・・・。 (MKさん)
A:(松本神父)
祈りの場には、どこでも水が用意されています。
インドのヒンズー教は、川で身を清めていますし、イスラム社会では、手や足を洗ってから寺院に入ります。
日本でも、神社やお寺には、水が用意され、手や口を洗って祈りの場に行きます。
教会も同じ。聖堂に入る時、聖水盤に指を浸し、十字架のしるしをしてから、洗礼の心になって、祈ります。
神さまにお会いするための心の姿勢です。
以前、神戸の教会にいた時、聖水盤が、灰皿になっていたのを思い出します。
見える聖水の十字架のしるしは、見えない神さまとお会いする愛のしるしです。
聖堂に入る時は、神さまにお会いする心を、聖堂を出る時には、祝福のされた心で過ごすために、 聖水で十字架のしるしをするのは、いいのではないでしょうか。
祈りの場には、どこでも水が用意されています。
インドのヒンズー教は、川で身を清めていますし、イスラム社会では、手や足を洗ってから寺院に入ります。
日本でも、神社やお寺には、水が用意され、手や口を洗って祈りの場に行きます。
教会も同じ。聖堂に入る時、聖水盤に指を浸し、十字架のしるしをしてから、洗礼の心になって、祈ります。
神さまにお会いするための心の姿勢です。
以前、神戸の教会にいた時、聖水盤が、灰皿になっていたのを思い出します。
見える聖水の十字架のしるしは、見えない神さまとお会いする愛のしるしです。
聖堂に入る時は、神さまにお会いする心を、聖堂を出る時には、祝福のされた心で過ごすために、 聖水で十字架のしるしをするのは、いいのではないでしょうか。
祖母に死後洗礼を授けたのですが有効でしょうか?
手続きはどうしたらよいでしょうか? (BYさん)
手続きはどうしたらよいでしょうか? (BYさん)
A:(松本神父)
洗礼は生きている者の恵み、神の子としての使命に生きる恵み、永遠の命の恵みです。
従って、一般的には、死後の洗礼は認められません。
しかし、故人が、生前、洗礼を望まれていたとか、好意を持たれていたとか、 家族が信者で、故人を守り、祈ってくださる時等、臨終に間に合わなくても、 司牧的な配慮から、死のすぐ後で、洗礼を授けることもなされていたようです。
しかし、教会法上認められていません。
ですから、信者の家庭で、未信者の方がおられたら、ご健在の時から、洗礼の大切さを話されて、理解していただけるようになさることです。
もし、重い病気で、入院されている場合、お元気な間に、司祭を呼ばれ、洗礼の恵みを受けることが大切です。
ぜひ、そうされますように。
洗礼は生きている者の恵み、神の子としての使命に生きる恵み、永遠の命の恵みです。
従って、一般的には、死後の洗礼は認められません。
しかし、故人が、生前、洗礼を望まれていたとか、好意を持たれていたとか、 家族が信者で、故人を守り、祈ってくださる時等、臨終に間に合わなくても、 司牧的な配慮から、死のすぐ後で、洗礼を授けることもなされていたようです。
しかし、教会法上認められていません。
ですから、信者の家庭で、未信者の方がおられたら、ご健在の時から、洗礼の大切さを話されて、理解していただけるようになさることです。
もし、重い病気で、入院されている場合、お元気な間に、司祭を呼ばれ、洗礼の恵みを受けることが大切です。
ぜひ、そうされますように。