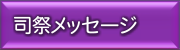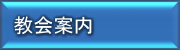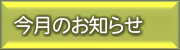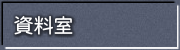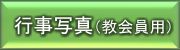2004年7月と8月のための聖書の一句
彼はお前の頭を砕く
ラウレンチオ 小池二郎神父
「お前と女、お前の子孫と女の子孫の間にわたしは敵意を置く。 彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。」 (「新共同訳」創世記3章15節)この一節は「原福音」と言われます。
最初にこう言った人は、教父の一人だと思いますが、今のところそれが誰かわたしは知りません。
ピオ12世教皇が、1950年11月1日の諸聖人祭に、「聖母マリアの被昇天」、 すなわち聖母マリアが、死後、霊肉ともに天に上げられたということは、 カトリック信者の信じるべき教義であるということを荘厳に宣言されました。 教皇はその宣言の大勅書 "ムニフィチェンティッシムス デウス" の中でも、 上の聖書の一節を原福音(プロト エヴァンジェリウム)と呼んでおられます。
大勅書の一部は次の通りです。 「すでに2世紀から、教父たちがマリアを新しいエワと呼んでいることを忘れてはならない。 彼女は新しいアダム(キリスト)に従属しており、 原福音(創世記3章15節)のにあるように、地獄の敵との激戦において、キリストに密接に結びついていた。 そして、異邦人の使徒(聖パウロ)の書簡において、 いつも結びつけられている罪と死(ローマの信徒への手紙5章6節、1コリント15章21節~26節、54節~57節)に完全に打勝ったのである。 したがって、キリストの栄光に輝く復活が、決定的勝利の本質的部分、最終的しるしであったのと同じように、 罪に対するキリストとマリアの共同の戦いもまた、 処女マリアの肉体の「栄光」によって終わりを飾ったのである。 『この死すべき人間が、不死を着る時、死は勝利に飲み込まれたという聖書の言葉が実現する』(1コリ15章54節)と使徒は言っている。」 (カトリック教会文書資料集3901) 今日は、創世記3章15節がなぜ原福音なのか、またこれがマリア様とどのような関わりをもつかを考えたいと思います。
最近のどの日本語訳もこの個所については大同小異ですが、少し違うものの代表として、フランシスコ会聖書研究書訳を引用します。
「わたしはおまえと女との間に、おまえの子孫と女の子孫との間に恨みをおく。かれはおまえの頭を踏みつけ、 おまえはかれのかかとにかみつくであろう。」(下線は筆者による)
ここに使われているヘブライ語は、「踏みつける」と「かみつく」が同じ動詞です。 フランシスコ会聖書研究所はそんなことは十分に知った上でこのように訳し分けているのだと思います。 このヘブライ語の動詞は、危害を与える場所によって、訳語を変えてもよいようです。しかしこれは今日の課題とはしません。
ピオ12世教皇が、1950年11月1日の諸聖人祭に、「聖母マリアの被昇天」、 すなわち聖母マリアが、死後、霊肉ともに天に上げられたということは、 カトリック信者の信じるべき教義であるということを荘厳に宣言されました。 教皇はその宣言の大勅書 "ムニフィチェンティッシムス デウス" の中でも、 上の聖書の一節を原福音(プロト エヴァンジェリウム)と呼んでおられます。
大勅書の一部は次の通りです。 「すでに2世紀から、教父たちがマリアを新しいエワと呼んでいることを忘れてはならない。 彼女は新しいアダム(キリスト)に従属しており、 原福音(創世記3章15節)のにあるように、地獄の敵との激戦において、キリストに密接に結びついていた。 そして、異邦人の使徒(聖パウロ)の書簡において、 いつも結びつけられている罪と死(ローマの信徒への手紙5章6節、1コリント15章21節~26節、54節~57節)に完全に打勝ったのである。 したがって、キリストの栄光に輝く復活が、決定的勝利の本質的部分、最終的しるしであったのと同じように、 罪に対するキリストとマリアの共同の戦いもまた、 処女マリアの肉体の「栄光」によって終わりを飾ったのである。 『この死すべき人間が、不死を着る時、死は勝利に飲み込まれたという聖書の言葉が実現する』(1コリ15章54節)と使徒は言っている。」 (カトリック教会文書資料集3901) 今日は、創世記3章15節がなぜ原福音なのか、またこれがマリア様とどのような関わりをもつかを考えたいと思います。
最近のどの日本語訳もこの個所については大同小異ですが、少し違うものの代表として、フランシスコ会聖書研究書訳を引用します。
「わたしはおまえと女との間に、おまえの子孫と女の子孫との間に恨みをおく。かれはおまえの頭を踏みつけ、 おまえはかれのかかとにかみつくであろう。」(下線は筆者による)
ここに使われているヘブライ語は、「踏みつける」と「かみつく」が同じ動詞です。 フランシスコ会聖書研究所はそんなことは十分に知った上でこのように訳し分けているのだと思います。 このヘブライ語の動詞は、危害を与える場所によって、訳語を変えてもよいようです。しかしこれは今日の課題とはしません。
2つの問題
蛇は何を指しているか。女は誰か。彼とは誰か。その3つが課題です。 蛇、これはサタンもしくは悪魔の隠喩(メタファー)です。
しかし、これはそれほど難しい問題ではありません。女は誰か、彼とは誰か、この2つが大問題です。
最初、蛇が女(後にエワと命名されます)を誘惑し、神が決して食べてはいけないと命じておいた木の実を食べるようにし向けます。
女は誘惑に負けてそれを食べ、さらに男を誘惑して食べさせます。 最初の男アダムはこの誘惑に負け、人類を代表して、大きい罪を犯すことになります。これが後に言われる原罪です。
神による罰の宣言は、最初に蛇、次に女、最後に男と罪を犯した順番になされます。
3章15節は蛇に対する宣告であり、これが原福音と呼ばれるようになりました。
この女は、一見、エワと考えるのが自然に見えますが、蛇に負けたばかりの女と蛇との敵対を直ちに予告するのも自然ではありません。
ここで創世記2章24節に出る男女を見ることにしましょう。 「男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。」 これは最初の女が最初の男の肋骨の1本から作られた物語に続く文章ですが、 この女はエワではありません。 わたしはある時、アダムは最初の人で父母がいないのに、 なぜ父母を離れることが出来たかという質問を受けたことがあります。 創世記2章24節の男女は、具体的なアダムとエワではありません。 同様に3章15節の女もエワその人ではありません。 その女は女性一般か、新約聖書を参考にすると、罪の対極にいるマリア様ではないでしょうか。 続く16節には再度エワとエワに続く女性が受ける罰が記されています。
ところで、聖書の解釈で、一番初めに考えるべきことは、その聖書が成立した当時の人がそれを読んで何を考えたかということです。 これは字義通りの意味と言われます。 しかし、もう一つの、特に、旧約聖書と聖書の黙示文学的個所を読むときに必要な考え方は、 文字の奥深くに含まれている意味、 あるいはより深い意味 (ラテン語で Sensus prenior, 英語で more than literal sense) が何かということです。 創世記3章15節の女は、字義的には女性一般、より深い意味では、聖母マリア様という説にわたしは賛成しています。
神による罰の宣言は、最初に蛇、次に女、最後に男と罪を犯した順番になされます。
3章15節は蛇に対する宣告であり、これが原福音と呼ばれるようになりました。
この女は、一見、エワと考えるのが自然に見えますが、蛇に負けたばかりの女と蛇との敵対を直ちに予告するのも自然ではありません。
ここで創世記2章24節に出る男女を見ることにしましょう。 「男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。」 これは最初の女が最初の男の肋骨の1本から作られた物語に続く文章ですが、 この女はエワではありません。 わたしはある時、アダムは最初の人で父母がいないのに、 なぜ父母を離れることが出来たかという質問を受けたことがあります。 創世記2章24節の男女は、具体的なアダムとエワではありません。 同様に3章15節の女もエワその人ではありません。 その女は女性一般か、新約聖書を参考にすると、罪の対極にいるマリア様ではないでしょうか。 続く16節には再度エワとエワに続く女性が受ける罰が記されています。
ところで、聖書の解釈で、一番初めに考えるべきことは、その聖書が成立した当時の人がそれを読んで何を考えたかということです。 これは字義通りの意味と言われます。 しかし、もう一つの、特に、旧約聖書と聖書の黙示文学的個所を読むときに必要な考え方は、 文字の奥深くに含まれている意味、 あるいはより深い意味 (ラテン語で Sensus prenior, 英語で more than literal sense) が何かということです。 創世記3章15節の女は、字義的には女性一般、より深い意味では、聖母マリア様という説にわたしは賛成しています。
彼とは誰か
蛇の頭を踏みつける女の子孫は誰でしょうか。 この子孫は、ラテン語のヴルガタ訳 《ヴルガタとは普及版という意味で、この場合固有名詞になっています。》 ではセーメン (種、中性名詞)、
日本語聖書の台本ヘブライ語聖書ではゼラ(種、男性名詞)、 ヴルガタ訳が参考にしたギリシャ語旧約聖書、セプトゥアジンタではスペルマ(種、中性名詞)です。
種は個人的にも集合的にも子孫の意味で使われます。 ヘブライ語聖書の種は男性名詞ですから問題はありませんが、ギリシャ語聖書の「種」(子孫)は中性名詞です。
ですからギリシャ語聖書ではそれを受ける代名詞「それ」は中性の "アウト" であることが期待されますが、 ここでは、「彼」 "アウトス" になっています。
もっとも、種は具体的には人間ですから、それを男性代名詞で受けているとする説もあります。 この場合、単数か複数かは分かりませんが、彼の先行詞は「人間」です。
しかし、権威のあるエルサレム聖書のこの個所の解説には、 集合的な意味のある子孫をあえて男性単数代名詞に受けさせているのは、一人の救世主を考えてのことだとしています。
いづれにしても、罪に完全に打つ勝つことの出来た人は、 イエス・キリスト以外にはいないのですから、 少なくともこの「彼」 "アウトス" は、少なくとも「より深いい意味において」イエス・キリストであるとする説にわたしは賛成です。
聖書の専門家、聖ヒエロニムス(347-420)が原語から一人で全訳を行ったと言われるヴルガタ訳では、 なぜかこの子孫を受ける代名詞が「それ」でも彼でもなく、彼女自身(イプサ)になっています。 なぜか。ここには出ませんが、子孫にあたるラテン語の女性名詞が二つあり、それとこれと関わりがあるのでしょうか。 しかし仮に「彼女自身」(イプサ)が一人の女性を指しているなら、 それは無原罪の聖母で、蛇の頭を足で抑えておられるご像ともよく合います。 しかし、それは聖書の読み方としては誤った深読みではないかと思います。 さて偉大な聖ヒエロニムスは何を考えていたのでしょうか。 現在のヴルガタ訳聖書は、ここのところを「彼」にしています。
聖書の専門家、聖ヒエロニムス(347-420)が原語から一人で全訳を行ったと言われるヴルガタ訳では、 なぜかこの子孫を受ける代名詞が「それ」でも彼でもなく、彼女自身(イプサ)になっています。 なぜか。ここには出ませんが、子孫にあたるラテン語の女性名詞が二つあり、それとこれと関わりがあるのでしょうか。 しかし仮に「彼女自身」(イプサ)が一人の女性を指しているなら、 それは無原罪の聖母で、蛇の頭を足で抑えておられるご像ともよく合います。 しかし、それは聖書の読み方としては誤った深読みではないかと思います。 さて偉大な聖ヒエロニムスは何を考えていたのでしょうか。 現在のヴルガタ訳聖書は、ここのところを「彼」にしています。